
- (受賞時)国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 准教授
(現在)同上
平原 秀一 氏 - 受賞テーマ:
『暗号の安全性の証明に向けた計算量理論の先駆的研究』 - 受賞理由など詳細はこちら
ヤマト科学は2014年の創業125周年を記念して、独創性、創造性に富む、気鋭の研究者を顕彰し、人類に夢と希望をもたらす科学技術の次世代リーダーとしての活躍を支援することを目的とした、ヤマト科学賞を設立いたしました。
第11回ヤマト科学賞の募集は終了いたしました。

ヤマト科学は1889年(明治22年)の創業以来、多種多様な商品と高い技術力を背景に、研究者の皆様のニーズに応えることで、我が国の科学技術の進歩発展に貢献してまいりました。
「ヤマト科学賞」は、創業125周年を迎えた2014年に、独創性、創造性に富む気鋭の研究者の更なる飛躍を支援することを目的として創設した賞です。
審査委員には各界を代表する著名な先生方にご就任頂き、各分野の優れた候補者の中から、毎回入念な討議を経て厳正に受賞者1名を決定しています。
科学技術創造立国を標榜する我が国において、熾烈な国際競争を勝ち抜くためには研究開発分野の活性化が不可欠であり、本賞が次世代リーダーとなる優れた研究者の発掘や育成にお役に立つことを願っております。
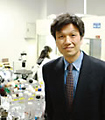
ヤマト科学賞は、日本を代表する研究科学機器メーカーのヤマト科学の後援で、21世紀のグローバルな科学の展開を日本からになう若手の発掘をめざすユニークな賞である。すでにエスタブリッシュした研究者を褒賞するのでなく、今、時代に先駆けた成果を得つつある気鋭の若手研究者に光をあて、社会に広く紹介しようという賞である。30代の気鋭の研究者を中心に主として20代から40代の研究者が中心的な対象になっている。主に、マテリアル、インフォーメーション、ライフのサイエンスが対象であるが、これまで確立している領域よりは、より複雑な、新たに生まれつつあるダブルやトリプルメジャーの領域が注目される。一つの手法でなく、結果や考え方がバッティングする新たな領域を育てていく研究者の応募を望んでいる。いわばシンギュラリティー後の科学を生み出そうという若手のための賞である。自薦、他薦をとわない広い門戸で、新たな萌芽を探す賞である。多くの気鋭の研究者の応募を期待する。

社会の持続、発展にはサイエンスを基礎とするイノベーションをたゆむことなく起こし続けていくことが必要です。そのためには若い諸君の柔軟な思考、過去にとらわれない発想が重要となります。
ヤマト科学賞はサイエンス分野における次世代のリーダーになるポテンシャルを持った若手を発掘・顕彰し、その後も様々な形で持続的な応援をすることを目的としています。
審査員の専門とする分野は、主としてマテリアルサイエンス、インフォメーションサイエンス、ライフサイエンスですが、それらにとらわれることなく、様々な分野、特に境界領域、融合領域の研究者からの応募も強く期待しています。

ヤマト科学賞の選考にあたり、若手研究者を元気づけることに最大の注意を払っています。「若手」とは、「成熟していない」という意味でもあります。
科学技術の進歩において、この「成熟していない」ということは非常に重要です。技術は成熟化すると、最適化が進み、ますます先鋭化していきます。それはそれでよいのですが、ちょっとした環境変化に対して適応できなくなっていくきらいがあります。科学技術には多様性が不可欠です。
これは生物の進化も同じで、恐竜まで進化した爬虫類が、弱々しく見えた哺乳類に主役をあけわたしたことを考えてみれば明らかでしょう。
若いということは、現在の本流に対して正面きって異を唱えられるということだと思います。その特権を利用して、科学技術の進化を支えていただきたいと思います。
第11回(2024年)受賞者

第10回(2023年)受賞者

第9回(2022年)受賞者

第8回(2021年)受賞者

第7回(2020年)受賞者


第6回(2019年)受賞者

第5回(2018年)受賞者

このたびはヤマト科学賞という大変栄誉ある賞をいただけたことを光栄に思います。
私の専門は理論物理学で、とくに熱力学の基本原理に関わる研究、いわば「なぜ時間に向きがあるのか」「情報を活用することで熱力学第二法則の限界を超えられるか」といった研究をしてきました。これはある意味で19世紀にまでさかのぼる非常に古いテーマですが、近年の様々な実験技術の進歩の影響もあり、この10年ほどで世界的に非常に活発な研究テーマになっています。
このような基礎的な研究を評価していただけ、今回栄誉ある賞をいただけたことを大変嬉しく思います。これからも、物理学と情報科学の境界領域の更なる深化・発展に貢献できるよう、全力を尽くしていきたいと思います。
第4回(2017年)受賞者

第3回(2016年)受賞者

ヤマト科学賞という輝かしい名誉をいただき、大変光栄です。私はこれまで工学研究者として世の中に役立つシステムを作ることを目指して、何が本質的な問題解決かを自問自答しながら研究を続けてきました。センシングシステムのための通信プロトコルの設計分野で研究者としてのキャリアをスタートしましたが、気づけばセンサ自身の製造技術から、エネルギーマネジメント、アプリケーションまでを広く扱うようになりました。分野を広げることは、専門性が浅くなる危険もありますが、このような形でチャレンジを認めていただいたことは大きな自信になりました。まだまだ「人類に夢と希望をもたらす」ような成果として結実したわけではありませんが、一歩でも近づけるよう精進したいと思います。
第2回(2015年)受賞者

ヤマト科学賞はライフサイエンス、マテリアルサイエンス、インフォメーションサイエンスやその融合分野から毎年一人だけ選ばれ大変名誉なことですが、それ以上に様々なバックグラウンドを持つ歴代の受賞者と交流の機会がありそれが大変刺激になります。
自分の場合は第1回受賞者のマテリアルサイエンス内田 健一先生、第3回受賞者の川原 圭博先生と話してその考え方に触れることができ、このような研究者と並んで受賞者に選ばれたことに対して改めて激励された気持ちになりました。研究者の皆様も応募に挑戦して頂きたいですし、気鋭の研究者をエンカレッジしたい方は是非推薦頂きたいと思います。
第1回(2014年)受賞者

東北大学金属材料研究所に助教として勤務していた2014年に、第1回ヤマト科学賞を拝受致しました。受賞時に森川社長、選考委員会の先生方から頂いた「これからの活躍が期待できる若手の助教が第1回の受賞者になって大変良かった」という旨のお言葉が、特に印象に残っています。肩書ではなく純粋に研究成果でご選考いただいたことに対して感謝すると共に、今後の活躍への期待が込められていることを深く受け止めています。
受賞テーマは熱流によるスピン流生成現象「スピンゼーベック効果」の発見と開拓に関するものですが、これまでの研究を発展させることのみならず、全く新しいインパクトのある研究を継続的に発信することが、このご期待に応える上で必須であると思っています。幸いなことに、2016年より物質・材料研究機構に移籍し、新たな研究を展開するためのスタートラインに立つことができました。ヤマト科学賞受賞者に恥じない研究者に成長できるよう、今後も精進していきます。