ヤマト科学は単純に製品を売るのではなく、開発のプロセスを共有してくれる。
機器を作る上でのインテグレーション機能を持っているところが、私は魅力だと感じています。
― 2017年10月25日
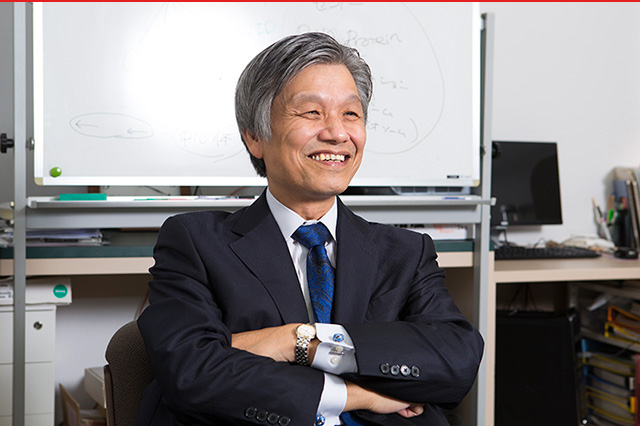
ヤマト科学は単純に製品を売るのではなく、開発のプロセスを共有してくれる。
機器を作る上でのインテグレーション機能を持っているところが、私は魅力だと感じています。
― 2017年10月25日
先端研はプロセスを重視するダイナミックなラボ
先端研はスタティックではなくダイナミックなラボです。ある結果ではなく、プロセスの理解に重きを置いていることがポイントです。例えばこの「フェロモンの結合予測」のアニメーションを見てください。
動画は、生理活性物質のフェロモン(以下、フェロモン)がフェロモン受容体タンパク(以下、受容体)に結合する過程を示しています。中央の大きな構造体は、受容体の立体構造を模式化したもので、フェロモンは化学構造で描かれています。
生体内では無数のタンパクが働いています。動画にある受容体もその一つです。
立体構造では模式化されていますが、タンパクは何万個もの原子・分子で構成されています。当然原子・分子は止まっているわけではなく、化学結合力や静電気力、分子間力によりいつも少しずつ位置を変えており、タンパクの周りにある水分子や脂質分子も同様の力の作用で影響し合い、少しずつ動き続けています。こうした力の働きをコンピュータで計算し、タンパク立体構造の経時的な変化を再現したものが、分子動力学シミュレーションといわれるものです。
※シミュレーション計算には膨大な演算能力を要するため、「京」レベルのスーパーコンピュータが必要となります。

動画を見ると、フェロモンは受容体の左側に滞在する時間が長い。しかしある時、受容体の下に来たフェロモンが受容体の中に取り込まれる。ここが重要で、スタティックに見ているとフェロモンが受容体の左に取り付くように見えてしまいますが、ダイナミックに観察すると、その結果はまったく違うことになります。これを創薬などに応用した場合、誤った設計をしてしまうことにもなる。だからプロセスを重んじダイナミックに研究することが必要で、そこが先端研の最たるポイントとなるのです。
これは僕自身の思考に対していえることでもあります。これまでの取り組みを振り返ると、動脈硬化の研究で『Nature』の表紙に載せてもらったり、慶應義塾大学経済学部の金子勝教授と『逆システム学』という本を書いたり、がんの創薬に関わってみたり、衆議院厚生労働委員会「放射線の健康への影響」の参考人説明で世間に衝撃を与えたり。振り返ってみると、まったく脈絡がないように感じます。しかし、すでに達成されてしまった結果より、いま直視すべき物事と、それを推し進めるためのプロセスを重視しているということです。
実は若い頃は結果が大事だと思っていましたが、ある経験で考え方が変わりました。1982年から90年までアメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)で必死に動脈硬化の遺伝子研究をしていたのですが、就労ビザが切れてしまい、帰国せざるを得なくなってしまいました。ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港を出るとき、僕は「5年間、よく頑張ったな」とこれまでを振り返りました。結果は出ていませんでしたが、不思議と自分がそれまで辿ったプロセスへの懐疑を感じなかったんです。
そんな気持ちで搭乗した飛行機の中でのことでした。アメリカを出国する前の実験結果を調べていたら、なんと動脈硬化の遺伝子(スカベンジャー受容体)を発見してしまった。無職で日本に戻るはずだったのに、帰国したら東大の教授になったわけです。「神様は見てくれている」という次元の話ではありますが、結果が後からついてきたことで、プロセスの重要性を身に沁みて感じましたね。
僕の研究室でも、「急ぐときは丁寧に」と言っています。自然科学というのは研究結果がいつ出るかわからない学問です。もちろん結果を重視する人もいますが、僕たち研究者がやろうとしているのは「今まで誰も解いたことのないものを解くこと」ですから、どんなに急いでいたとしても、プロセスは大切にしなければなりません。それも、意外性を生み出すプロセスこそが、価値ある研究結果につながるものであると僕は思っています。結果予測が立つようなら大した研究ではないということですから。
ヤマト科学は開発プロセスを共有できるメーカー

僕が初めてヤマト科学を知ったのは、東京大学の医学部生として研究室に足を踏み入れたときです。1970年代のことですが、その頃にはもうヤマト科学の恒温槽やインキュベータ、シェーカーなどの機器がごろごろと置いてありました。正直に言って当時は何の会社なのかよく分かっていませんでしたが、今思えば、その頃からすでに日本における理科学機器の主要メーカーだったということでしょう。
本格的なお付き合いが始まったのは、先端研の教授になってからです。動脈硬化や血管の内皮細胞の研究をしていて、今もシステム生物医学の分野で生命の流れを解き明かそうという取り組みを続けていますが、当時は21世紀に突入してヒトゲノムが解読されたことで、あらゆるデータをダイナミックに扱えるようになったタイミングでした。
ところが、ダイナミックにデータを収集しようとすれば機器に求める要素も複雑になり、「どのようにして人間の遺伝子のデータを取るか」という問題が同時に出てきたのです。細胞の相互作用を見たかったのですが、それを実現するには人体内のような環境下で細胞を培養する機器を作らなければなりませんでした。
いろいろなメーカーに相談をしましたよ。でも、どこも挫折してしまった。もちろんそうした機器を作るためにはあらゆる条件を満たさねばなりませんから、断念するのも無理からぬことです。例えば、脈波を作るにはポンプのようなものが必要ですが、ポンプで送り出してしまえばメカニカルな機構上、細胞が潰れてしまう。そうした互いにバッティングする条件をクリアする必要がありました。その無理を引き受け、共同開発を実現させてくれたのがヤマト科学でした。ヒトゲノムが解読されて以来、同社とは連携を強めています。
.jpg)
「細胞混合培養装置 MK2000」という機器ですね。簡単に説明してしまうと、人間の血管壁を培養で再構築するもの。しかも培地などではなく、実際すべてが生きている条件にしたかったわけです。
当時、僕は動脈硬化発症までの過程で見られる、単球が内膜に潜り込んでいく様子を再現しようとしていたのですが、それが非常に大変でした。先ほども述べましたが、脈波を作るだとか混合培養するだとか、そういった要求がいちいちバッティングしてしまうんです。「こっちを立てればあっちがダメになる」というようにね。しかも安い予算で作れと言うわけですから、メーカーからすればめちゃくちゃなニーズですよ。
けれども、そうした条件をクリアしてくれるのがヤマト科学。機器メーカーにとって大変なのは、個々のニーズに対応することではありません。それは現在の技術を持ってすれば実現可能なことですから。
例えば、「AIで自動運転すれば人間はいらなくなるか?」という議論をよく耳にしますが、個人的には実現できないと感じています。考えてみれば分かると思いますが、「速く走る」と「安全に走る」と「燃費を抑える」という要求はバッティングします。2つ程度の要求であれば均衡点を導き出せるかもしれませんが、これが3つ4つと増えていった場合、これらをインテグレートするには人間との対話で実現していくほかありません。
ヤマト科学との共同開発には、この対話があるのです。「プラスチック部品ならこの会社がいい」とか「培養にはこういうものがある」とか、そうしたマルチディシプリンをアセンブルして機器を作ってくれます。研究者である僕たちへのインターフェース機能を持っている、とても珍しいメーカーなのではないでしょうか。
ヤマト科学は単純に製品を売るのではなく、開発のプロセスを共有してくれる会社です。「この技術に秀でている」という会社ではありませんが、だからこそ面白い。機器を作るうえでのインテグレーション機能を持っているところが、僕は魅力だと感じます。おかげでダイナミズムのどのステップからでもデータを取れるようになりましたし、僕らは論文を書くことができた。その機器を使って博士になった院生で、東大の教授になった人もいますよ。
ヤマト科学賞の評価対象は新領域を開拓する気鋭の研究
ヤマト科学は2014年で創立125周年を迎えましたが、そのとき森川社長の「21世紀にふさわしい、新しい科学を生み出す研究者を応援する賞をつくりたい」「イノベーションを生み出すような賞にしたい」という思いを知りました。
総合科学技術・イノベーション会議議員の橋本和仁さん、Twitterで「あの人」として有名な日本におけるVRの第一人者の廣瀬通孝さん、そして僕と森川社長の4人で、「分野に関係なく、まだエスタブリッシュしていない人を選ぶ変わった賞を作りましょう」ということで始まったんです。
マテリアル、インフォメーション、ライフというまったく違う分野の研究者が3人集まったのは、スタティックな科学ではなく、ダイナミックな科学を生み出した研究者を評価するためです。これからの研究者は、ヤマト科学の製品開発過程がそうであるように、マルチディシプリンをインテグレートすることが求められる、いわゆるダブルメジャーが注目されるような時代です。
孔子の『論語』に「三十にして立つ」という言葉がありますよね。高度成長期には若い人が前向きに突き進んでいましたが、バブルが弾けたあとの失われた20年は、若者に投資しないという雰囲気がこの国にはあったと思いませんか。
賞を作るときに考えていたのは、三十にして立たなくなってしまうのが日本のサイエンスの弱点ではないか、ということでした。文化勲章やノーベル賞のような成功を讃える賞をヤマト科学でやる必要はない。ヤマト科学賞は、新たなサイエンスを切り開こうとする、気鋭の若き研究者が「立つ」ための応援をする賞なんです。
そして風変わりなことに、この賞では受賞者が次々に選考委員に加わっていく仕組みになっています。若い研究者に、彼らの視点で「こいつは伸びそうだ」という人を見つけてきてもらうわけです。どこまでも若い人のための賞、と言ってもいいかもしれませんね。当初は得体の知れないものだったかもしれませんが、どんどん応募者数も増えてきました。中にはノーベル賞級の研究者の推薦文を持ってくる人もいるんですよ。
ただし、繰り返しになりますが、ヤマト科学賞は成功を讃えるための賞ではないのです。選考にも明確な基準はありません。応募いただく研究成果は論文でも製品でもいいし、概念や数式でも構わない。僕たち選考委員が注目しているのは、とにかく新しい分野を生み出そうとしているチャレンジングな研究者、ダブルメジャーに挑戦しようとしている研究者です。「三十にして立つ」という保証はないけれど、この賞をきっかけに、新しいダイナミズムが生まれることを願っています。
これからは情報科学でもスペシャリストに
これからの時代で最も大変なのは、情報科学との向き合い方ではないでしょうか。ヤマト科学はもともとモノに強いですし、プロセスの部分も得意としている会社だと認識しています。しかし、情報科学の進展には凄まじいものがありますから、「機器と情報をどう結びつけていくか」というところで、従来とは違った姿を求められるのではないかと思います。
きっと、これまで扱ったことのないような大量のデータを取得し、大量の情報を流し続けなければならなくなるでしょう。そうなったときメーカーは、情報科学を脇でちょこっと使うのではなく、情報科学のスペシャリストにならなければなりません。先ほどヤマト科学賞のお話で「これからはダブルメジャーが注目される時代」と言いましたが、これはメーカーも同じで、情報科学それ自体の企業という側面も持たねばならないと思うのです。これまでとはまったく違う新たなチャレンジになるでしょうけれど、ヤマト科学には大いに期待しています。
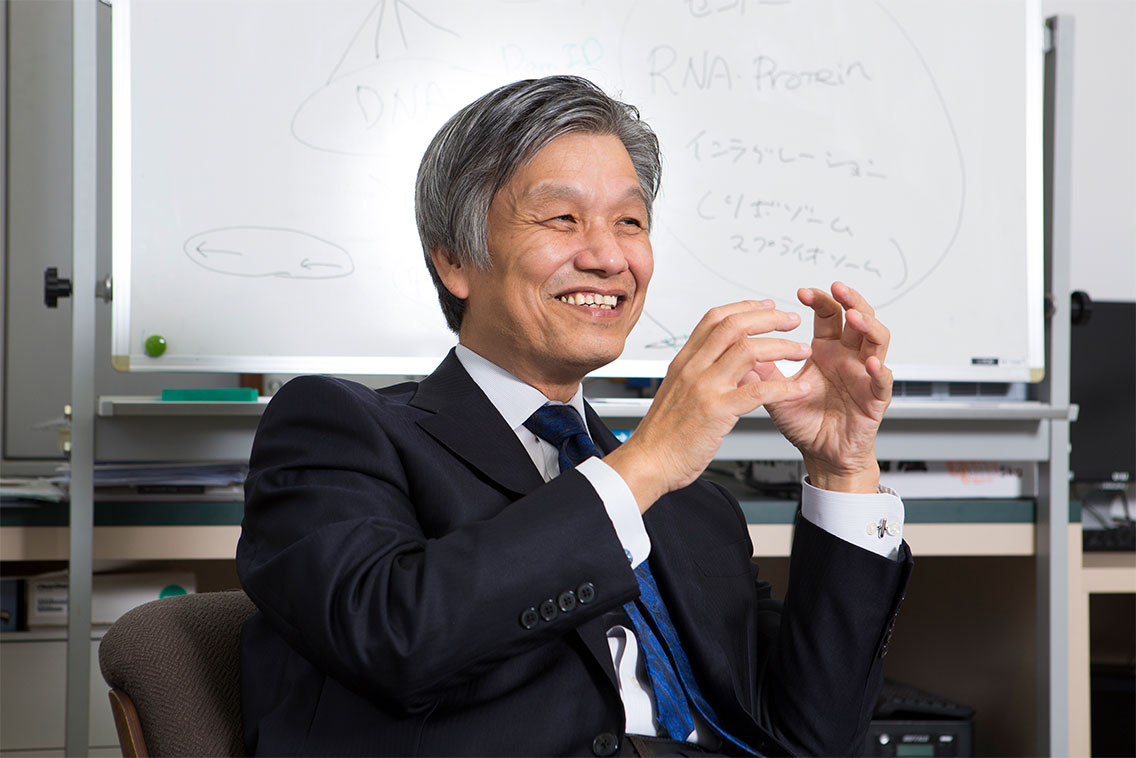
環境分析から事業領域を拡大し、高薬理活性医薬品の分析ニーズにお応えできるようになりました。 ― ...

ひとつでも多くのイノベーションを生み出す場所へ ― 新研究開発拠点の計画内容についておしえてくだ...

中央実験台は棚高さ可変加工により、分析機器の高さに合わせてスペースを有効活用できます。 納...

北陸・福井から全国へイノベーションを生み出すNIC 「NICCAイノベーションセンター(NIC)」は、...

デザイナーが果たす役割とは素直に製品と向かい合うこと 「ヒュームフード」という実験設備のお...

100人定員のセミナー会場に160人が詰めかけた 森川 2017年9月に幕張メッセで開催された分析・科...
